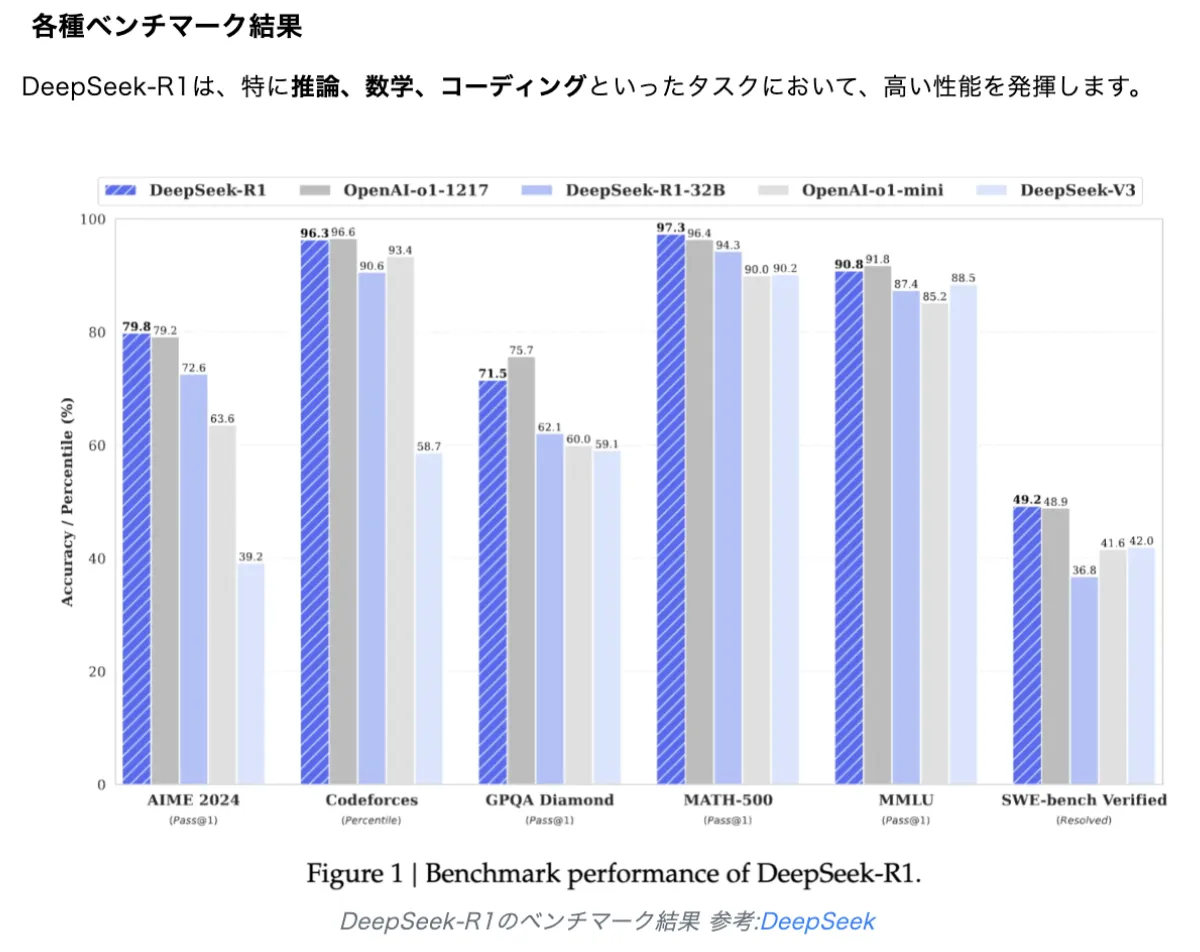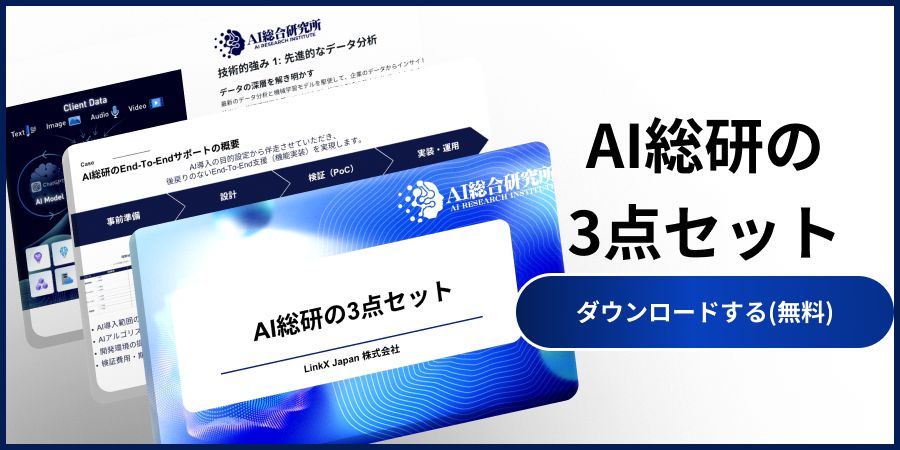この記事のポイント
配膳ロボットは飲食業界での人手不足解消や感染症対策に寄与
最新では、猫型や大きなスクリーン、自律移動技術やセンサー技術を搭載
導入事例として飲食業界や医療現場での活用が進む
業務効率化やサービス品質向上が期待される
導入には初期費用や店舗設計との相性、オペレーション統合の課題がある

Microsoft AIパートナー、LinkX Japan代表。東京工業大学大学院で技術経営修士取得、研究領域:自然言語処理、金融工学。NHK放送技術研究所でAI、ブロックチェーン研究に従事。学会発表、国際ジャーナル投稿、経営情報学会全国研究発表大会にて優秀賞受賞。シンガポールでのIT、Web3事業の創業と経営を経て、LinkX Japan株式会社を創業。
配膳ロボットは、飲食業界を中心に急速に注目を集めている自律移動型のロボットです。感染症対策や人手不足解消に寄与し、業務効率化やサービス品質向上が期待されています。この記事では、配膳ロボットの技術的な特徴や導入事例、メリット・デメリットについて詳しく解説します。
目次
配膳ロボットとは?注目が集まる背景
近年、飲食業界を中心に急速に注目を集めているのが「配膳ロボット」です。注文された料理を自律的に運ぶこのロボットは、単なる人手不足対策としてだけでなく、非接触でのサービス提供や業務効率化にも貢献しています。
特に、感染症対策の観点から 「人との接触を最小限に抑えたサービス」 が求められる中、配膳ロボットはその課題をスマートに解決する存在として広がりを見せています。
さらに、外食業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の一環としても導入が進んでおり、「人とロボットの協働」が現場の新しいスタンダードになりつつあります。
代表的な配膳ロボット4選(猫型も含む)
現在、日本の飲食店で活躍している主な配膳ロボットには以下のような機種があります。
猫型配膳ロボット: BellaBot(ベラボット)

BellaBot(ベラボット)
BellaBotは、Pudu社が考案した世界各国で活躍中の猫型ロボット。可愛らしいデザインと音声案内機能により、子どもから高齢者まで親しまれています。
PEANUT(ピーナッツ)

PEANUT(ピーナッツ)
中国KEENON Robotics社製で、狭い通路でも稼働可能な設計。幸楽苑や焼肉チェーン店で導入されており、通路幅50cmでもスムーズに動ける点が特長です。
ソフトバンクロボティクス Servi(サービィ)

Servi(サービィ)
ソフトバンクロボティクスとBear Robotics社が共同開発。天井のマーカーが不要で、AIによる自己学習型のルート走行が可能。焼肉きんぐ、デニーズなどに導入。
大きなスクリーン: LuckiBot Pro

大きなスクリーンが印象的なLuckiBot Proは、AIによる自律走行と音声案内機能を搭載。
各配膳ロボットの特徴比較
ロボットにはそれぞれ異なる特徴があります。以下に、主な配膳ロボットの比較を示します。
| ロボット名 | メーカー | 主な特徴 | 稼働時間 | 導入事例 |
|---|---|---|---|---|
| BellaBot | Pudu Robotics | 猫型デザイン、音声案内、最大40kg積載、SLAM自律移動、長時間稼働 | 12〜24時間 | すかいらーく(ガスト・しゃぶ葉) |
| PEANUT | KEENON Robotics | 狭小空間対応、天井マーカー誘導、抗菌コーティング | 非公開(長時間対応) | 幸楽苑・焼肉チェーン店 |
| Servi | SoftBank Robotics × Bear Robotics | 3Dカメラ+LiDAR、自動復帰、丸型トレイ、直感操作 | 10〜12時間 | 焼肉きんぐ・デニーズ |
| LuckiBot Pro | OrionStar Robotics | 最大60kg積載、大型スクリーン、音声認識、カスタマイズ性高 | 14〜16時間 | 居酒屋・ファミレスなど |
技術的な特徴
配膳ロボットには、最新の自律移動技術やセンサー技術が組み込まれています。
-
自律移動(SLAM)技術
店内の地図を作成しながら現在地を推定するSLAM技術により、障害物や人の動きを避けてスムーズに配膳が可能。 -
障害物検知センサー
赤外線・超音波センサーにより、人や物にぶつからないよう自動で停止・迂回します。 -
簡易なコミュニケーション機能
音声や表情表示を通じて、顧客と簡単なインタラクションを取ることができ、接客の一部も担えるようになっています。
これらの組み合わせと、AIによる学習機能により、ロボットは自律的に動きながらも、店舗の特性や顧客のニーズに応じた柔軟な対応が可能です。
導入事例と活用の広がり
すでに多くの飲食店で導入されている配膳ロボットですが、その活用範囲は飲食業界にとどまらず、医療や介護、物流など多岐にわたります。
飲食業界での導入事例
日本国内では、大手飲食チェーンを中心に配膳ロボットの導入が加速しています。
-
すかいらーくグループ(ガスト・しゃぶ葉など)
全国の約2,100店舗で、約3,000台のBellaBotが稼働中。人手不足対策だけでなく、顧客満足度の向上にもつながっています。 -
焼肉きんぐ・デニーズ
Serviを導入し、注文から配膳までの業務負荷を軽減。スタッフは接客に集中できるため、サービスの質が向上しています。 -
幸楽苑・焼肉の和民など
PEANUTを採用し、通路の狭い店舗でも問題なく運用。混雑時のピークでも安定した配膳が可能に。
医療・介護・物流分野への展開
配膳ロボットは、飲食業界にとどまらず、医療や物流など他分野でも活用が広がりつつあります。
医療現場での事例
- 日本医科大学千葉北総病院では、新型コロナウイルス対応の専門病棟において、ソフトバンクロボティクス製の「Servi アイリスエディション」を導入。
感染リスクのある病室への配膳・搬送業務をロボットが担うことで、医療従事者の安全確保と業務効率化を両立しています。
工場や倉庫での搬送支援
- 配膳ロボットの技術は、工場内の部品搬送や倉庫内のピッキング支援にも応用されており、「省力化ロボット」として生産性向上に寄与。
人手不足が深刻な製造業や物流業界でも、SLAMベースの自律移動ロボットの導入が進んでいます。
配膳ロボット導入のメリット
配膳ロボットには実際どのようなメリットがあるのでしょうか。
以下に、ご紹介します。
人手不足の解消と従業員の負担軽減
繁忙時間帯のホール業務や重い食器の持ち運びをロボットが代行することで、スタッフの身体的・精神的負荷を軽減できます。
業務効率とサービス品質の向上
配膳の時間短縮や配膳ミスの削減が、店舗の回転率向上と顧客満足度向上につながります。スタッフは接客や衛生管理などに専念できます。
感染対策としての非接触運用
特に医療現場や高齢者施設では、人との接触を減らすことが重要視されており、ロボットによる配膳が有効な対策となります。
導入の課題と注意点
一方で、配膳ロボットの導入にはいくつかの課題も存在します。
以下に導入の際の注意点を挙げます。
初期費用と運用コスト
導入にあたっては、1台あたり数十万円〜数百万円の初期投資が必要です。また、保守・メンテナンス、月額利用料が発生する場合もあり、ROIの検証が求められます。
店舗設計との相性
ロボットがスムーズに移動できる通路幅や段差の有無、障害物の位置など、店舗の構造との整合性が必要です。必要に応じて改装が求められることもあります。
オペレーションとの統合
ロボットと人間の業務分担を明確にしないと、かえって混乱を招く恐れも。導入時にはスタッフへの研修と運用ルールの整備が不可欠です。
まとめ|配膳ロボットは次世代サービスの象徴
配膳ロボットは、飲食業界の人手不足を補うだけでなく、サービスの品質と効率の両立を可能にする強力なツールです。さらに医療、物流、介護など他分野にもその活用は拡大しており、「ロボットと人間が共に働く社会」の実現を象徴する存在となっています。
今後もAIやセンシング技術の進化により、ロボットはさらに高機能化・多機能化していくと予想されます。業務の一部を自動化しつつ、スタッフが本来注力すべき業務に集中できる環境づくりに、配膳ロボットは大きな役割を果たすでしょう。
AI総合研究所は企業のAI導入を支援し、最新の技術情報や導入事例を提供しています。配膳ロボットに関するご相談や導入検討については、お気軽にお問い合わせください。