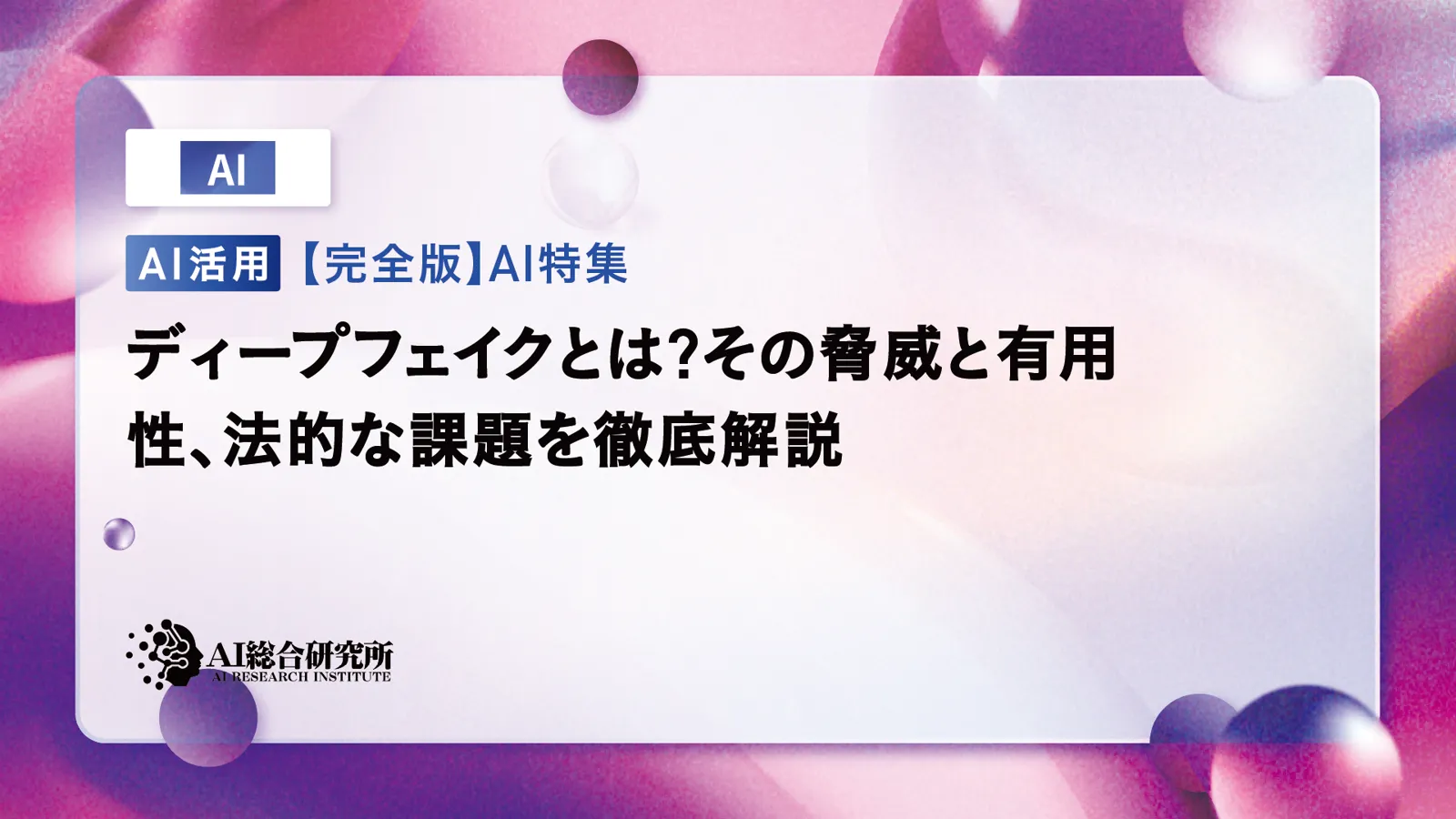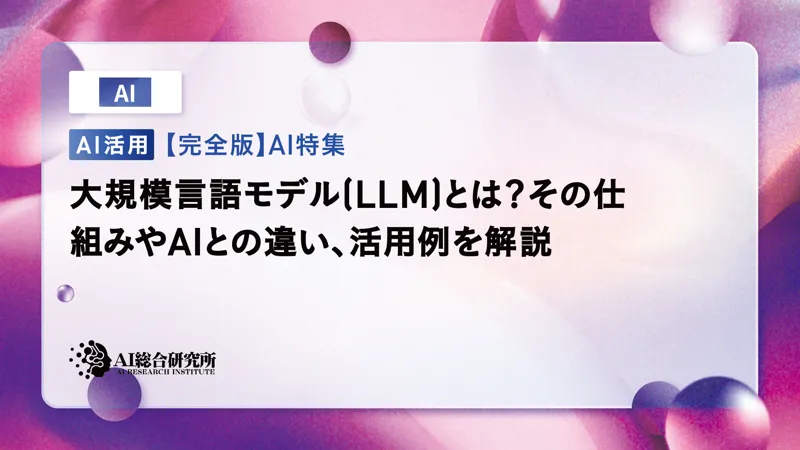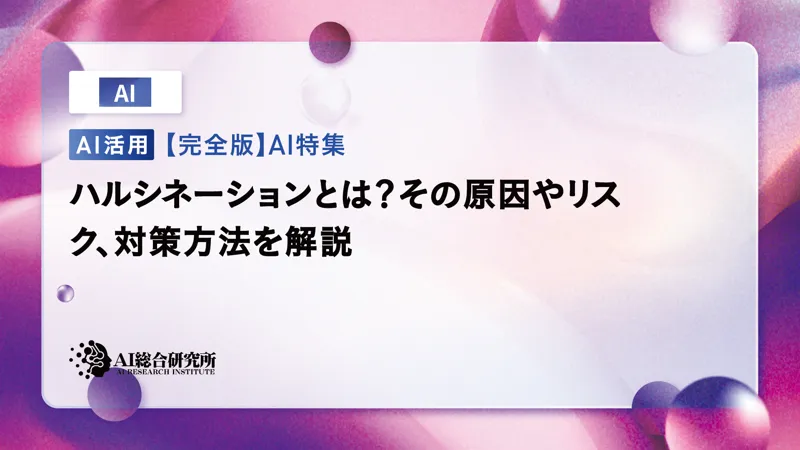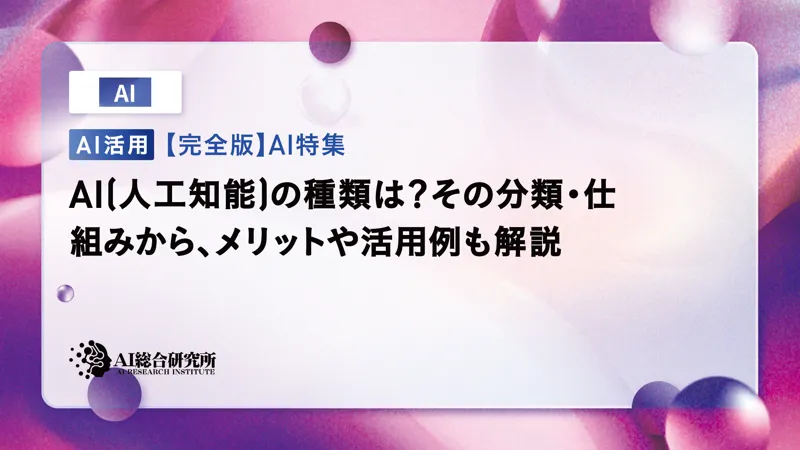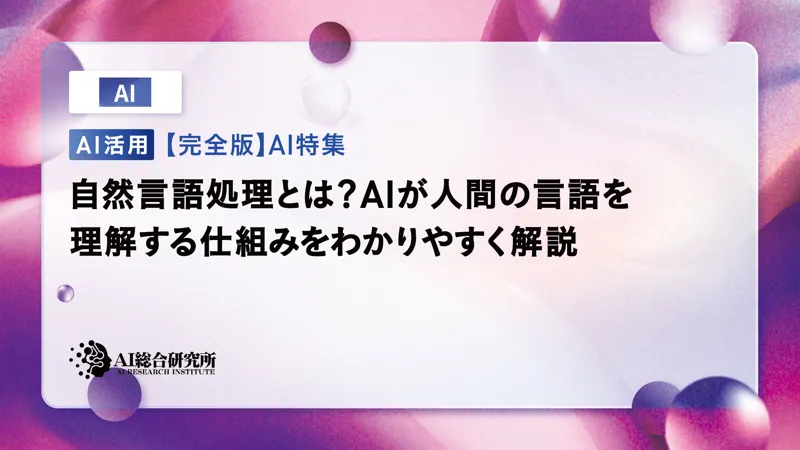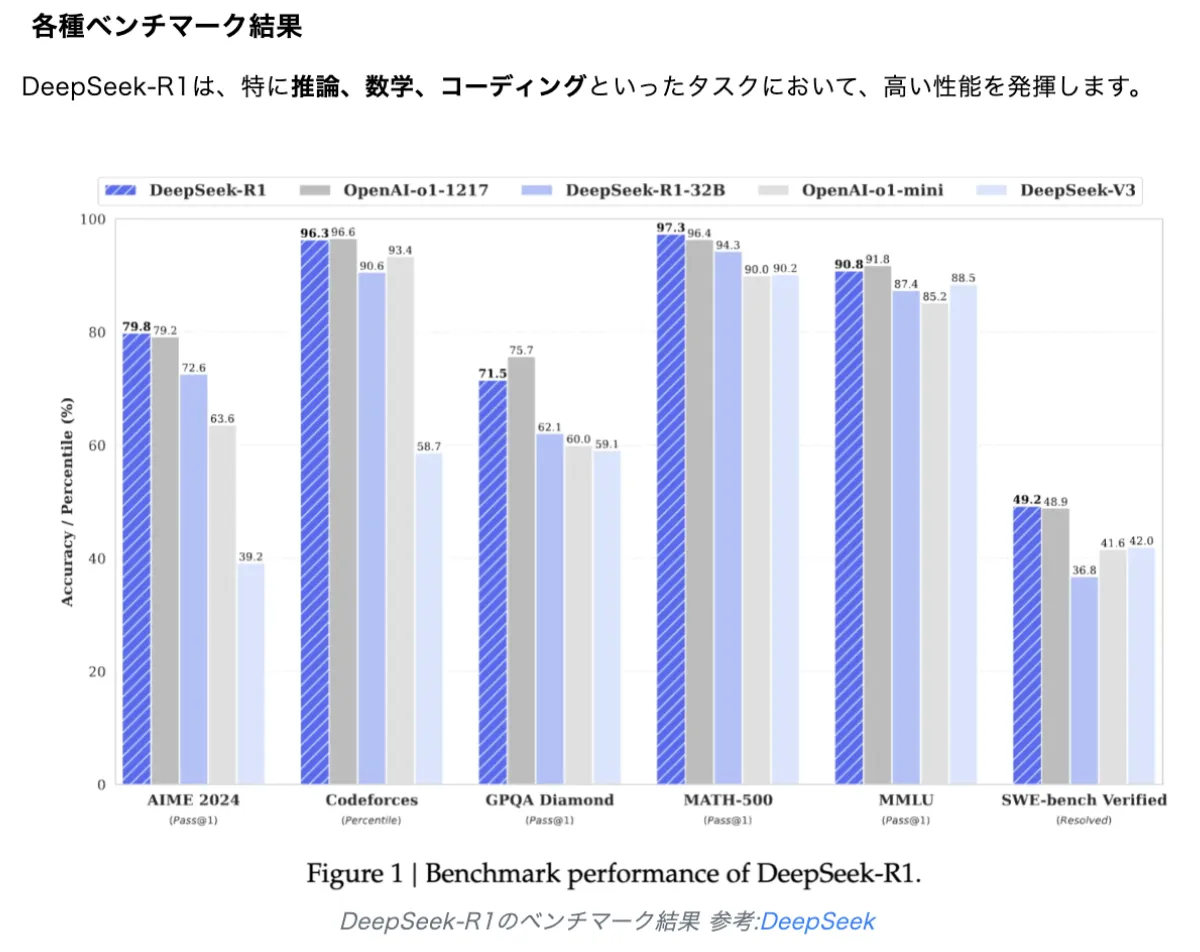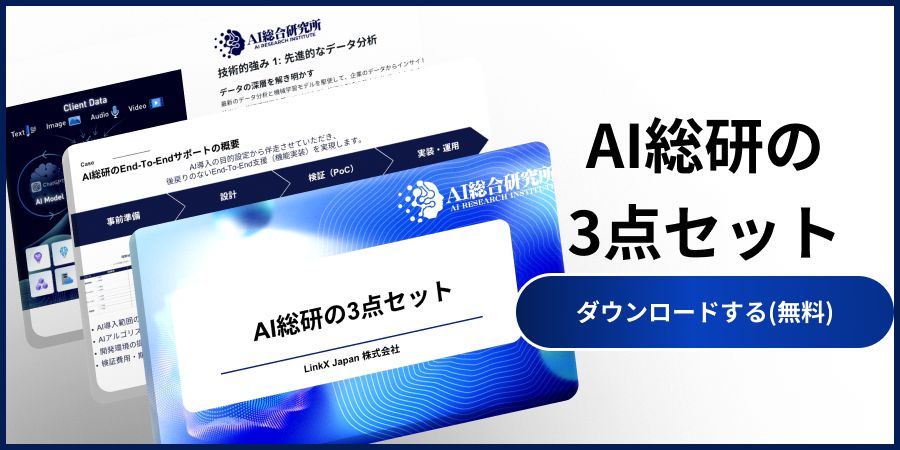この記事のポイント
AIトレスとは、AIが生成した画像をなぞって(トレースして)イラストを描く行為。
構図やポーズの参考として活用され、作画効率の向上や初心者の練習用素材として人気。
AIトレスには著作権侵害やオリジナリティの欠如の懸念があり、商用利用やコンテスト応募時には注意が必要。
AIトレスを利用する場合は、出典の明示やオリジナル要素の追加など、誠実な姿勢とルールを守ることが信頼性につながる。

Microsoft AIパートナー、LinkX Japan代表。東京工業大学大学院で技術経営修士取得、研究領域:自然言語処理、金融工学。NHK放送技術研究所でAI、ブロックチェーン研究に従事。学会発表、国際ジャーナル投稿、経営情報学会全国研究発表大会にて優秀賞受賞。シンガポールでのIT、Web3事業の創業と経営を経て、LinkX Japan株式会社を創業。
生成AIが一般に広まる中、「AIトレス」という言葉がイラスト業界・SNS・同人界隈で注目を集めています。
AIトレスとは、AIが作成した画像を参考にしてトレース(なぞる)し、手描きイラストとして完成させる行為です。
この手法は、「効率的で便利」と評価される一方で、「著作権侵害では?」「オリジナルとは言えない」といった懸念も広がっており、今や創作の新たな境界線となっています。
本記事では、AIトレスの意味、手法、倫理・法的リスク、社会的な受け止め方、AIトレス絵師問題など、 現場で今何が起きているのかを詳しく解説します。
AIトレスとは?
AIトレスとは、AIが生成した画像をトレース(模写)してイラストを描く行為を指します。
ここでいう「トレース」とは、構図・ポーズ・輪郭・陰影・光源配置などをそのまま、あるいは一部改変して手動で線画化・着彩することを意味します。
なぜ注目されているのか?
- Midjourney、Stable Diffusionなどの画像生成AIの普及
- 商業レベルの画力に近づける時短手法としての人気
- 「AIが描いた」とは言わず手描き風に見せる事例の急増
絵を描くとき、「もう少し上手にポーズを決めたい」「構図のアイデアが浮かばない」と感じたこと、ありませんか?
そんなときに、AIで作った画像を参考にして描き始める——それが、いわゆるAIトレスというやり方です。
やり方はシンプルです。まずはMidjourneyやStable Diffusion、などで自分のイメージに合う画像を生成します。
その画像を下描きとして使い、線をなぞったり、構図だけを参考にしたりして自分の絵を描いていく。最後に色を塗ったり、表情や細部を加えたりして、自分なりの作品に仕上げていく。 この流れをざっくり言えば「AIトレス」です。
この手法、最近ではさまざまな目的で使われています。
たとえば、まだ絵に慣れていない人が人体のバランスを学ぶために使うこともありますし、同人活動や仕事での制作スピードを上げるための時間短縮にも役立ちます。
何より、自分では思いつかなかったようなポーズや世界観に出会えることもある。それがAI画像を起点にする面白さでもあります。
ただ、AIトレスには注意も必要で、問題も生じています。
とくに気をつけたいのは著作権や倫理面
AIが学習している元データには、アニメやゲーム、漫画などの既存作品が含まれている可能性があり、それに似た構図をそのままなぞってしまうと、意図せず“盗作”に見られてしまうこともあるでしょう。
さらに、出来上がった絵を「完全に自作」として公開したり、コンテストに応募したりすれば、大きなトラブルに発展しかねません。
ネット上では「AIトレス絵師」と呼ばれる人たちが注目されることもあります。
ただ、その注目が必ずしもポジティブなものとは限らず、「AIに頼っているのに、それを隠している」と見られると、炎上してしまうのが現状です。
法律の観点では、AIが自動で作った画像そのものに著作権があるかどうかはまだ議論が続いています。ただ、他人の作品にあまりにも似ていたり、明らかに既存キャラクターの構図を写していたりすれば、やはりトラブルになるリスクは避けられません。
だからこそ大切なのは、「どう使うか」 です。
多様な意見がありますが、AI画像を参考にすること必ずしも悪いわけではないでしょう。しかし、それを公にする場では「これはAI画像をベースにしました」と明記したり、コンテストなどでは完全に自分で描いたものだけを出すようにするなど、誠実な態度が求められます。
絵を描くことは、自己表現であると同時に、他者との信頼関係でもあります。
だからこそ、AIトレスという新しい道具を使うときにも、「自分がどうありたいか」「何を伝えたいか」を忘れずにいたい。
透明性、説明責任、そしてちょっとの勇気。それさえあれば、AIトレスも立派な創作の一部として、きっと受け入れられていくのではないでしょうか。